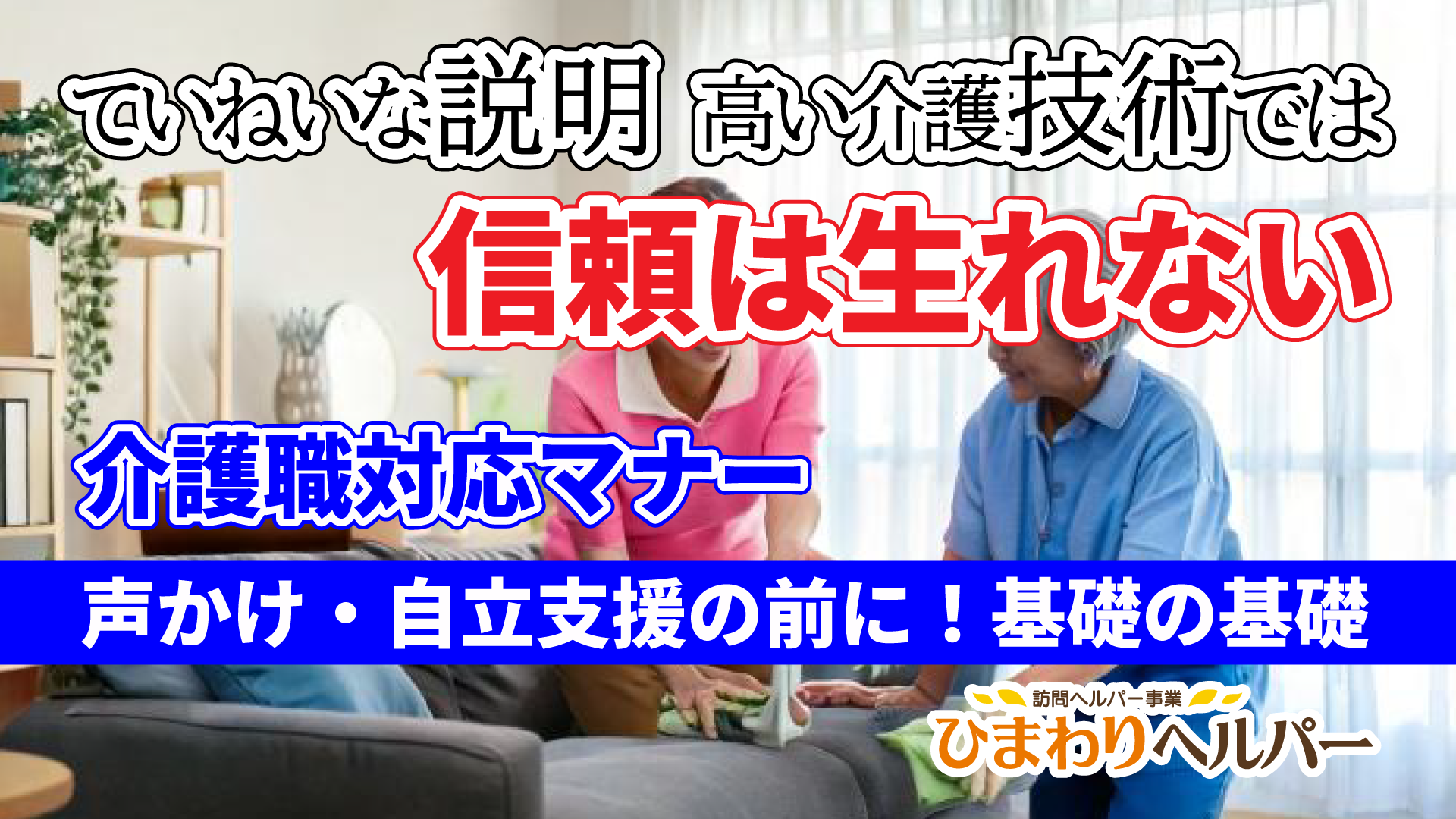
あなたなら どう応える?
突然ですが 質問です! あなたならこんなお客さまに どう対処しますか?

「娘たちは私を見捨てるつもりなの」
とつぶやいた 子どもは別居 それぞれ子育でや夫の親の介護に忙しい
頻繁に帰省しないが 年1~2回帰省している
あなたが訪問ヘルパーの立場だったら どう答えるのが適切だと思いますか?
- 「そんなことはありませんよ。優しい娘さんじゃないですか~!」
- 「どうしてそんな風に思うのですか~?」
- 「娘さんたちも忙しいんですよ。そんなこといったら もう来てくれなくなりますよ~(笑)」
- スルーして 別の話題に変える
教科書的な正解は「B」でしょうか?
だけど 実際の現場では ”無駄話”するヒマなんてないよね?
みんな 「正解」や「マニュアル」を求めがち だけど 人の感情はマニュアル通りにはいきません 時と場合によっていろんな返答があり得ます
「正解」を求め お客さまの感情を軽視していませんか?
「自立支援」を押し付けていませんか?
「自分の感情」を優先させていませんか?
お客さまへの対応の仕方をしっかり考えましょう
対応の仕方=接遇 なぜ大事?
介護技術や知識と同じくらい大切なのが 利用者さんへの対応の仕方=接遇 です
結論を言えば ぶっちゃけ”見た目の雰囲気”です
「また 身も蓋もないことを…」とお思いですか? だけど 想像してみてください
あなただって

自宅に”ヤバそうな人”を 入れたくないですよね?
それと同じこと!
初めてのお客さまに

怖い人だったら どうしよう…
受入れられなかったら どうしよう…

こんな事考えている場合ではありません これでは”ド素人”です
介護職であれ 医療職であれ 人と接する仕事は「接客業」です
お客さまやそのご家族さまに
「安心できる」「親身になってくれる」
と感じてもらえるように関わることが第一
これがいわゆる「接遇」です 「ユマニチュード」という言葉を知っていますか? まさにそのことなのですが 日本風に言えば「接遇」です
「接遇」ができ 受け入れられて初めて 「自立支援」を考えます
これができていない介護職・医療職の方がとても多いと感じます
「接遇」は「お世辞」や「おべっか」と思われがち だけど違います 一瞬でお客様の信用を失いかねない 非常にデリケートな問題 「”接遇”ができない人は 介護職はできない」と言っても過言ではありません
”見た目の雰囲気”の作り方!
「傾聴」「共感」介護で習いますよね?
だけど! これは往々にして理想論です 特に要介護の場合 現場は「傾聴」とか やっているヒマ ないですよね? 「ユマニチュード」意味わかりませんよね?
じゃあ どうする? 日本風に分かりやすく言い換えれば
100の言葉より 1回のアイコンタクト
お客さまの正面をみて 敬意もって 頷けばいいんです ぶっちゃけ 見た目の「雰囲気」です 多くのお客さまの信頼は 0.5秒で決まってしまうんです
基本ポイント
- 外見:身なりを整える
- 目線:ビビらずちゃんと相手の正面を見る
- 自立:「この人はできる」と思い込む
- 傾聴:敬意を忘れず できない理由を聞く
- 表情:状況に応じた表情
この5つを意識するだけで お客さまの気持ちや行動は大きく変わります
だけど いちいち全部覚えられませんよね?
そんな時どうする? そう!
100の言葉より 1回のアイコンタクト
練習してみよう
お客さまが「もう年だから何もできないよ」と言ったとき
あなたならどう対応する?
NG①「そんなことありませんよ!」(否定だけ)
NG②「そう思っているんですね」(共感だけで終わる)
OK 「ご自身でお茶を入れられますよね? 今日も一緒にやってみませんか?」
「小さな挑戦」をプラスすると自立支援につながる
だけど
100の言葉より 1回のアイコンタクト!
「お客さまの正面をみて 敬意もって 頷く」
指の巧緻性が障害され 箸で食事ができなくなったお客さま
あなたならどう対応する?
NG①:「私が食べさせますね!」
NG②:「だったら 食べるのやめますか?」
OK:「スプーンならご自分で食べられそうです やってみませんか?」
「小さな挑戦」をプラスすると自立支援につながる
だけど
100の言葉より 1回のアイコンタクト!
「お客さまの正面をみて 敬意もって 頷く」
腰痛で掃除や家事ができなくなったお客さま
あなたならどう対応する?
NG:「私が全部やります」
OK:「机の上はAさんにお願いして 私は下を拭きますね」
「小さな挑戦」をプラスすると自立支援につながる
だけど
100の言葉より 1回のアイコンタクト!
「お客さまの正面をみて 敬意もって 頷く」
👉 お客さまの「できること」を一緒に見つけるのが大切です
が!
100の言葉より 1回のアイコンタクト!
「お客さまの正面をみて 敬意もって 頷く」姿勢が一番大事!
これって勘違いフレンドリー⁉ NG対応に注意!
基本的に お客さまは介護員に「恐怖を感じている」と思っていてちょうどいいです 皆さんだって エアコン修理に”ヤバそうな人”が自宅に来たら 怖いでしょう?

学習の場では 分かった気になるんだけど 実際に現場ではとても多いです 本当に気をつけましょう
勘違いフレンドリー01「子ども扱い」
「よくできました!」
「〇〇しちゃダメでしょ!」
「うんち出たぁ?」など
砕けた表現で親近感を演出する人 多いと思います これを私は「勘違いフレンドリー」と呼んでいます 喜ぶお客さまもいますが 実は我慢している方も多いです だからこそ ヘルパー自身が自省しなければ 気づかないのです
こう言われて ご家族様はいい気はしません 「上司に使わない言葉遣いは ダメ」と覚えておけばよいでしょう
それぞれ「すごいですね!」「〇〇しては のちのち困りませんか?」「今日は(排便)出ましたか?」のように言い換えます
勘違いフレンドリー02「呼び捨て」「あだ名」
「〇〇ちゃ~ん」
「〇〇爺さん」
「〇〇婆」など
これもかなり多いと思います 施設で多い印象でしょうか 喜ぶお客さまがいるのも事実 だけど 「勘違いフレンドリー」です 我慢している人も多いです 家族はいい気はしません これも「上司に使わない言葉遣いは ダメ」と覚えておきましょう
勘違いフレンドリー03「”うんうん”相槌」
医療・介護業界に限らず めちゃくちゃ多いです 親身になっている感じを出す「勘違いフレンドリー」の典型例です ”分かってる感を出したい”ケアマネさんに多い印象でしょうか だとしたら大失敗です 絶対にやめましょう
偽コミュ障「無表情・ため息」
”困難事例”と称される方や ぶっちゃけ”性格悪い”お客さんもいますし ”過保護なケアプラン”など やるせない気持ちはわかります だけど「私たちは接客業」 忘れないように!
”陽キャ”だって表情作るのは疲れます! 「自分は陰キャ・コミュ障だから」は言い訳 単なる怠慢ですよ!
安心安全バカ「過保護な”危ないからやってあげる”」
「勘違いフレンドリー」の医療・介護職の方よりはマシですが 「自立支援」を忘れてはなりません
往々にして「過保護」にすると お客さまは喜びます だから なんだか信頼感が得られた気になりますが それは勘違いです 「全部やってあげる」とお客さまは あなたのことを「女中さん」と思うようになります 一度「女中さん」と思われたら最後 絶対に自立支援はできません くれぐれも注意してくださいね
これらは 尊厳を傷つけるだけでなく お客さまの自立の芽をつぶすことになります 気をつけましょうね
トラブル・クレームの真の原因とは?

「あのヘルパーは もうウチに よこさないで!」
お客さまに こう言われたくありませんよね? だけど みなさん知っていましたか?
お客さまからのクレームがヘルパー変更や事業所変更の理由の一つです
クレームの原因は概ね次のような感じ
- (あのヘルパーは)
- 挨拶もしない
- 調理が不味い
- 掃除が雑
- 忙しそうだから 話ができない etc.
たいてい こういう表現です
では ヘルパーさんは本当に「挨拶もしない」「調理が不味い」「掃除が雑」「話できない」のでしょうか?
「挨拶の研修」「調理の研修」「掃除の研修」をしても あまり意味がありません!
なぜなら
本当の理由は「挨拶」「調理」「掃除」などではないからです!
お客様の言葉を そのまま鵜呑みにしてはダメ!!
皆さん こういう気持ち分かりますか?
尿漏れして気持ち悪かったが 異性のヘルパーさんに恥ずかしくて言えなかった…
次から 同性のヘルパーに変えてもらおう
こんな気持ち 分かりますか? だけど ヘルパーさんには 何の悪いことしていませんよね?
これと全く同じことが言えます
お客様の多くは 「思い」を正確に表現しているとは限りません
その言葉の奥には…
- そのまま言うと恥ずかしい
- プライドが傷つく
- 波風を立たせたくない
- ヘルパーからの仕返しが怖い…
等など さまざまな思いがあるのです 素直に言えないのです
だから ”妙に上から目線”になったり ”遠まわし過ぎて伝わらなかったり”するのです
忘れないでください
お客さまの言葉を そのまま鵜呑みにしては ダメ!
クレームの原因は 実は”接遇”=対応の仕方の場合がほとんどです
だから
100の言葉より 1回のアイコンタクト!
人は「見た目」が一番!
いくら手早く掃除や調理ができても 信頼は生まれない
お客様の言われた通り正確に行っても 信頼は生まれない
だってお客様が「ああ言った」「こう言った」はナンセンス
人間の判断は 8割見た目 2割が音や臭いなどです
ほとんどの方は論理的な言葉は通じません なぜなら人間は理屈じゃなく感情で生きているからです
では 感情のはどこから生まれてくるのか? ほとんどの人は 「見た目」なのです
人気のヘルパーさんを思い浮かべてみてください その多くは 見た目や仕草が良いからではありませんか?
要するに 見た目の「接遇」がよければ クレームはあまり起きないのです
だから
- 外見:身なりを整えましょう
- 目線:ビビらずちゃんと相手の正面を見ましょう
- 自立:「この人はできる」と信じれば 自然とできる人オーラが生れます
- 傾聴:”フリ”でいいです 見た目に敬意を示しましょう
- 表情:表情は見た目に一番関わります
100の言葉より 1回のアイコンタクト!が本当に大切なのです
まとめ:自立支援につながる接遇
プロの介護職と素人との違いは「自立支援」の観点があるかどうかです しかし ”上から目線”で「自立」を押し付けては お客さまに受け入れられません 技術・知識より大切なのが 接遇なのです
一番大切なのは ぶっちゃけ”見た目の雰囲気”です それができて初めて 信頼感が生れます これがいわゆる「接遇」です フランス風に言えば「ユマニチュード」
「接遇」ができて初めて 「自立支援」を考えます
「接遇」は「お世辞」や「おべっか」とは違います 日本風「ユマニチュード」 お客さまを軽視せず かと言ってヘルパーも卑屈にならない 相手を「一人前の大人」と扱うことで お客さまにも「一人前の大人」の心が芽生えるのです
「接遇」のためのチェックリストは次の通りです
- 外見:身なりを整える
- 目線:ビビらずちゃんと相手の正面を見る
- 自立:「この人はできる」と思い込む
- 傾聴:敬意を忘れず できない理由を聞く
- 表情:状況に応じた表情
要するに
100の言葉より 1回のアイコンタクト!
今日の「接遇」が 明日の「できた!」につながります
